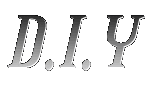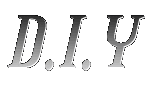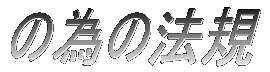|
���@�A�d�ʂ̕ω��� |
| ���͈͓� |
���͈͒��� |
| �w�蕔�i |
�ȈՂȎ�t���@ |
�葱�s�v |
�葱�s�v |
| �Œ�I��t���@ |
�葱�s�v |
�葱�s�v |
| �P�v�I��t���@ |
�葱�s�v |
�葱���K�v |
| �w��O���i |
�ȈՂȎ�t���@ |
�葱�s�v |
�葱�s�v |
| �Œ�I��t���@ |
�葱�s�v |
�葱���K�v |
| �P�v�I��t���@ |
�葱�s�v |
�葱���K�v |
���̒i�K�ł͂悭�����ł��܂��A�Ƃɂ����u���͈͓��v�ł���u�葱���s�v�I�v���ƁI
�����Ō����u���͈́v�Ƃ͉��̕\�B
���͈͂̋敪
|
���� |
�� |
���� |
�ԗ��d�� |
| �����Ώیy�����ԁA���^������ |
�}3cm |
�}2cm |
�}4cm |
�}50kg |
| ���ʎ����ԁA��^���ꎩ���� |
�}100kg |
�Ȃ�قǁA�悭�u�I�[�o�[�t�F���_�[�͕Б�10mm�܂�OK�I�v�Ȃ�ĕ����̂́A���̎��Ȃ�ł��ˁI
���āA�ł́u���͈́v������̂ł��A�u�ȈՂȎ�t���@�v�A�w�蕔�i�ɂ����ẮA����Ɂu�Œ�I��t���@�v�ł���A�葱���s�v�ł��ƁI�Ȃ�̎����ƌ����ƁA�u�w�蕔�i�v�Ƃ́A�w���[�U�[�̚n�D�ɂ��lj��A�ύX������W�R���������A���S�̊m�ہA���Q�̖h�~��x�Ⴊ���Ȃ��ʓr��߂������ԕ��i�B�x�������ŁA������Ƀ��X�g�A�b�v���Ă���܂��B�y�w�蕔�i���X�g�z
����ȊO���u�w��O���i�v�ƌĂԂ����ł��B
�ł́A��t���@�̋敪�͈ȉ��̒ʂ�B
- �ȈՂȎ�t���@�F��ɂ����t������@�B
- �Œ�I��t���@�F�{���g�E�i�b�g��A�ڒ��܂ɂ����́B
- �P�v�I��t���@�F�n�ږ��̓��x�b�g�ɂ����t������@�B
�����ԁA���C�y�ȋC���ɂȂ��Ă��܂�����@���A
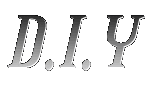
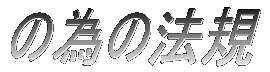

�Ԍ��ƋL�ړ��e���Ⴄ�ꍇ�́A�L�ڕύX�Ȃǂ̎葱�������Ȃ���Ȃ�܂���B
���̍ہA��r�I�ȒP�Ȃ̂��A
�@�P�D�I�[�o�[�t�F���_�[�ɂ��ԕ��ύX
�@�Q�D�㕔���ȓP���Ȃǂɂ���Ԓ���̕ύX
�炵���ł��B
����ȊO�ɂ��u�����v�Ɋւ�鍀�ڂ́u�����v�A�u�����v�A�u���q�d�ʁv�A�u�����@�̌`���v�A�u���r�C�ʖ��͒�i�o�́v�Ȃǂ̍��ڂ͂���܂����A��������ۂ̎��q�ƋL�ړ��e�������ĂȂ��Ă͂Ȃ�܂���B
���A2007�N11��22���ɋK���̊ɘa������A��������ɂ����Ă͌y���ȉ����Ƃ��āA�L�ڕύX�A�\���ύX�����Ȃ��Ă��悭�Ȃ����̂ł��I
�S�D���Ⴀ�A�\���ύX�����K�v�Ȍy������Ȃ��������āH
�P�D�܂��́A�Ԍ��ƋL�ړ��e�������Ă邩�H
���ӁF����͂����܂Ŗ@�K�ɑ��Ă̌l�I���߂ł��B�����ɏ����Ă��鎖�����ׂĐ������Ƃ͌���܂���B�����܂ł��Q�l���x�ɂ��l�����������B
�����A���낻��Ԍ��I����Ȏ��ɋC�ɂȂ�̂��A���܂Ŏ{����DIY���ʂ����ĎԌ��ɒʂ�̂��ۂ��B�Ⴆ�u�w�b�h���X�g���ߍ��^�̃��j�^�[�͎Ԍ��ɒʂ�Ȃ��B����A�ʂ�v�ȂǁA���̕��X��HP�����Ă��ӌ��͕�����Ă��܂��B
�����ŁA�����ł͋C�ɂȂ�@�K��O�ꌤ���I
�����������ł����B�B�B����ł́A�ۈ��DIY�ʂɌ������Ă݂悤�I

����́A�����Ԍ����@�l���K�肷��u�R�������K��v�ɂ������I
���F���F�R�������K��@��W�́u�G���v�ʓY�P�u���������ԐR���v�́v��47������ ����20�N10��15����蔲��
�����̓R�����g
�R �D���������Ԃ̓͏o�̕K�v�Ȕ͈�
�⋭�i�V�̃t�F���_�[��肩���͂Q�T�O�����܂ŁI
�i�P �j �Ԙg�y�юԑ�
�Ԙg�y�юԑ̂ɂ��āA���ɊY������������s������
�@ �t���[����L���鎩���Ԃ̃t���[���`���ύX�i �t���[���̌`��i ��F �X�g���[�@�g�̃L�b�N�_�E���j���͒f�ʌ`��i��F�R�`�́��@�`�j��ύX������̂������j�A�@�y�уz�C�[���x�[�X�Ԃ̃t���[�����������͒Z�k�������
�A ���m�R�b�N�\���̎ԑ̂̕ύX���s�����̂Ŏ��ɊY������������s������
�E���m�R�b�N�\���̎ԑ̂ɒ��a���Q�T�O mm �̉~�͈̔͂��āA�����͐茇����݂������̂ł����āA�J�������͂�⋭���Ȃ�����
�E���m�R�b�N�\���̎ԑ̂̌`��^�� �y�^�ɂ������
�E���m�R�b�N�\���̃A���_�[�{�f�B���̓��[�t��ύX���A�^�]�Ҏ��A�q���y�щב���������͒Z�k�������
�E���m�R�b�N�\���̎ԑ̂̃t�����g�E�I�[�o�[�n���O�����̓��A�E�I�[�o�[�n���O�����������͒Z�k�������
�E�捇�����ԓ��̃��m�R�b�N�\���̎�v���i�\����ύX�������
�B ��֎����Ԃ��瑤�ԕt��֎����ԂɕύX���s������
�G���W���`���A�r�C�ʂ��������Ă���A�ڂ������Ă��\���ύX�ɂȂ�Ȃ��I
�i�Q �j �����@
�����@�ɂ��āA���ɊY������������s������
�@ �^���̈قȂ錴���@�ɏ悹���������
�A �����@�̑��r�C�ʂ�ύX�������
MT��AT�ڂ������́A�c�O�Ȃ���\���ύX���K�v�B
�i�R �j ���͓`�B���u
���͓`�B���u�ɂ��āA���ɊY������������s������
�@ �v���y���V���t�g�̕ύX�i �v���y���V���t�g�̐��@���͍ގ���ύX������̂������j ���s������
�A �h���C�u�V���t�g�̕ύX�i �h���C�u�V���t�g�̐��@���͍ގ���ύX������̂������j ���s������
�B �g�����X�~�b�V�����̕ύX���s�����̂Ŏ��ɊY������������s������
�E�蓮���g�����X�~�b�V������ �������g�����X�~�b�V����
�E�` �^�g�����X�~�b�V������ �a �^�g�����X�~�b�V�����i �������A�ϑ��䖔�͕ϑ��i�̕ύX��������̂������B�j
�E�@�B���N���b�`�� �d���N���b�`�i �������A�N���b�`�������^���ɕύX������̂͏����B�j
�C �쓮�����̕ύX�i�쓮����������������s�����̂������j ���s������
�D �쓮���ւ̓��͓`�B�����̕ύX�i �`�F�[������ �x���g���A�`�F�[�������̓x���g���� �h���C�u�V���t�g���j���s������
�i�S �j ���s���u
���s���u�ɂ��āA���ɊY������������s������
�@ ���s�����̕ύX�i�^�C���̃L���^�s�����͂���j���s������
�A �t�����g�E�A�N�X�����̓����E�A�N�X���̕ύX���s������
�B �����̕ύX���s������
�i�T �j ���c���u
���c���u�ɂ��āA���ɊY������������s������
�@ ������n���h���̈ʒu�̕ύX�i �E�n���h���� ���n���h���A������n���h���̒lj��j ���s������
�A ���ǎ����̕ύX�i�Q �v �r �̂S �v �r �j ���s������
�B �����N���u�̕ύX�i �M���{�b�N�X�A���b�h�A�A�[���ދy�уi�b�N���̎�t�ʒu��ύX������́j ���s������
�C �����摀������̕ύX�i �����摀��������蓮�����瑫�����ɕύX������́j���s������
�����Ɍ����ƁA�L�����p�[�ύX��[�^�[�ύX���\���ύX���K�v�Ƃ́I
�Ƃ͌����A�^�u���[�L���[�J�[�́u�����Ԃ̋K���ɘa�ɔ����m���Ɏ�t�����Ă������������Ă��Ă��Ԍ��ɂ͒ʂ�܂��B�v�Ƃ���������Ă���܂��B
�i�U �j �������u
���������̕ύX���s�����̂Ŏ��ɊY������������s������
�E�h�����E�u���[�L�� �f�B�X�N�E�u���[�L
�E�����g������ �O�����k��
�E�������� ��C���@���j ���̏ꍇ�ɂ����ẮA�����͏o��v���Ȃ����̂Ƃ���B
�E�u���[�L�y�_���A�u���[�L���o�[�A�}�X�^�[�V�����_�y�уz�C�[���V�����_�A�{�͑��u�A�u���[�L�E�J���A�u���[�L�h�����A�f�B�X�N�E�u���[�L�̃L�����p�[�y�у��[�^�[�A�e��̖����i
��C���j �ٓ���ύX��������
�i�V �j �ɏՑ��u
�ɏՑ��u�ɂ��āA���ɊY������������s������
�@ �ɏՑ��u�̎�ނ̕ύX�i �R�C���X�v�����O�� ���[�t�X�v�����O�� �g�[�V�����X�v�����O�� �E�H�[�L���O�r�[���� �g���j�I���� �G�A�i �����j
�T�X�y���V�����j ���s������
�A�ɏՑ��u�̌��˕����i���[�t�X�v�����O�̖���������ύX�������B�j�̕ύX�i ���[�t�X�v�����O�A�u���P�b�g�A�V���b�N���A�T�X�y���V�����A�[�����̓i�b�N���T�|�[�g�̕ύX���s�����́j
���s������
�i�W �j �A�����u
���������Ԃ̎吧�����u�ƘA�����č�p����\���̎吧�����u�������팡�������Ԗ��͂�����������錡�������Ԃ̘A�����u�̎�t���A�A����{�̂̕ύX���͉������s�����̂Ŏ��ɊY������������s������
�E��T�֎��A����̎�t���A�A����{�̂̕ύX���͉������s������
�E�s���g���t�b�N���A����̎�t���A�A����{�̂̕ύX���͉������s������
�E�x���}�E�X���A����̎�t���A�A����{�̂̕ύX���͉������s������
�E�q�b�`�{�[�����A����̎�t���A�A����{�̂̕ύX���͉������s������
�i�X �j �R�����u
�R���̎�ނ�ύX����������s�����̂Ŏ��ɊY������������s������
�E�K�\������ �y���� �k �o �K�X�i �k �o �f �j �� ���k�V�R�K�X�i �b �m �f �j �� ���^�m�[���� �d�C�� ���̑��̔R��
�E�n�C�u���b�h
�i�P �O �j ���̑�
��L�i �P �j ����i �X �j �̊e���ɊY������������s���ꍇ�ɂ����āA����^�����ɐݒ肪���鑕�u������t�����@��ύX���邱�ƂȂ��g�p������̂ɂ��ẮA�͏o�ɌW��Y�t�����̂����v�Z���y�ы��x�������̒�o��v���Ȃ����̂Ƃ���B
�������A�������͔r�o�K�X�K�����قȂ邱�Ƃɂ��ʌ^���Ƃ��Ă�����̂ɂ����Ă�����^���Ƃ݂Ȃ��Ď�舵���č����x���Ȃ����̂Ƃ���B
�R�D�������I�I�w�蕔�i�ƌ����ǂ��A�ۈ�������Ȃ���A
�Ԍ��͒ʂ�Ȃ��I
�Q�D�\���ύX�̕K�v�̂Ȃ��y���ȉ����͂��ꂾ�I
"tm_house" Copyright, Tomo, 2008.